~介護休業・介護休暇・介護保険制度のこと、わかりやすくお話しします~
はじめに
「介護保険」って聞いたことありますか? 40歳を過ぎると保険料を納めるので、なんとなく耳にしたことがあるかもしれませんね。
この制度は、基本的には“介護を受ける人”のためのものです。
では、もし会社員のあなたが、突然「親の介護をしなきゃいけない」となったとき、使える制度があることをご存じでしょうか?
実は、介護休業や介護休暇という制度があって、一定の条件を満たせば誰でも利用できるんです。
「うちの会社にはそんな制度ないよ〜」と思った方も安心してください。これは国が法律で定めた制度なので、すべての会社が対象です。
それぞれの目的や内容を知って、あらかじめ自分の会社でどのように使えるのかを確認しておけば、いざというときにも安心です。
日本における仕事と介護の現状
日本は今、超高齢社会を迎えています。
それに伴って、働きながら家族の介護をしている人が増えています。
2000年(介護保険スタートの年)には約256万人だったのが、2019年には約658万人にまで増え、今も増え続けています。
核家族化や少子化により、介護を担う家族が減っている一方で、介護のために仕事を辞める「介護離職」も増え、社会問題となっています。
そして、「働きながら介護できる制度がある」ことを知らない人が多いのが現実です。
介護離職の現実
「仕事を辞めれば介護に集中できて、むしろ楽かも…」と思うかもしれません。
でも実際は、精神的にも身体的にも、そして経済的にも、しんどさが増す人が多いのです。
調査によると、介護のために離職した人の5割以上が、精神的・身体的・経済的な負担が増えたと答えています。
🧠 精神的な負担
介護のために仕事を辞めると、社会とのつながりが減ります。仕事をしていると物理的に介護から離れる時間ができ気持ちの切り替えができますが、仕事を辞めることで介護中心の生活になります。これが長く続くと精神的にも辛くなり、介護ストレスもたまりやすくなります。
💪 身体的な負担
介護には基本的に休みがありません。
排泄・入浴などの介助は体力が必要ですし、
特に重度の認知症や寝たきりの方を一人で介護すると、心身ともに疲労が蓄積します。
仕事をしていると、介護サービスを活用したり、家族で分担したりできますが、
離職すると「全部自分でやらなきゃ」という思い込みが生まれ、負担が一層重くなることも。
💸 経済的な負担
介護を理由に会社を退職した場合、雇用保険に加入している一定の条件を満たす人であれば失業給付が受けられます。
この場合退職理由や介護の状況により、すぐに給付が始まる特定理由離職者になるか、給付制限のある自己都合離職者になるか異なります。
特定理由離職者はそれを証明するための書類が必要で、その判断はハローワークが行います。
このように失業給付を受けることはできますが、手続きの手間、収入の減少、期間限定の給付といった理由から経済的負担が増すのは明らかです。
介護にはお金がかかります。デイサービスやショートステイなどの介護保険サービス費、介護保険対象外で実費となる食事代や部屋代、医療費、オムツ代など介護のための固定支出は少なくないでしょう。
介護のために仕事を辞めてから、介護がひと段落した後に再就職するという方法がありますが、現実的にはかなりハードルが高いことです。
調査によると介護離職後に再就職ができた人は半数程度です。特に親の介護が始まる多くは50代で、その年代での再就職はさらに厳しくなるでしょう。
「介護休業」ってなに?
✅ 家族の介護体制を整えるためのお休み(通算93日・3回まで分割OK)
✅ 休業前の賃金の67%を給付(雇用保険加入者)
✅ 申請は勤務先へ。開始予定日の2週間前までに申請が必要
介護休業は、あくまで「介護の仕組みづくり」のための制度です。
ずっと介護するためではなく、「どうすれば続けられるか」を考える準備期間なんですね。
だから、復職が前提となっています。
「介護休暇」って?
✅ 1日・時間単位で取得可能
✅ 年5日まで(家族が2人以上なら最大10日)
✅ 有給か無給かは会社の就業規則による
通院やケアマネさんとの面談、役所での手続きなど、
ちょっとした用事に使いやすい制度です。
無給でも「出勤扱い」となるため、有給取得率や賞与などに影響しません。
介護保険を活用するには?
✅ 65歳以上なら申請できる(要介護認定が必要)
✅ 市区町村の窓口で手続き。結果が出るまで1〜2ヶ月程度
✅ 在宅介護にも施設介護にも利用可能
在宅介護では、デイサービスやヘルパー、介護ベッドのレンタルなど、
複数のサービスを組み合わせて利用することが多いです。
訪問診療、配食、見守り、民間の有料サービスなどを取り入れれば、
在宅介護の負担を軽減できます。
一方、施設介護は家族の負担は減るけれど、費用が高めです。
特別養護老人ホーム(特養)は費用が抑えられますが、入所待ちが多い傾向にあります。
仕事と介護を両立するために
✅ 介護制度や会社の規定を事前にチェック
✅ 信頼できるケアマネジャーとの関係づくり
✅ 働き方や予定を家族・支援者と共有
✅ 親の性格や希望を普段から把握
✅ 一人で抱え込まず、話せる相手を見つけておく
そして、なにより大切なのは……
親には親の、あなたにはあなたの人生があること。
決して1人では抱え込まないでください。
おわりに
介護が始まるということは、大切な人とのお別れの時間が、
少しずつ近づいているということでもあります。
だからこそ、その時間をどう過ごすかが大切です。
介護に“完璧”はありません。
でも、「自分なりにできた」と思えることが、
その後の自分を支えてくれるはずです。
ここまで読んでいただき、ありがとうございました.
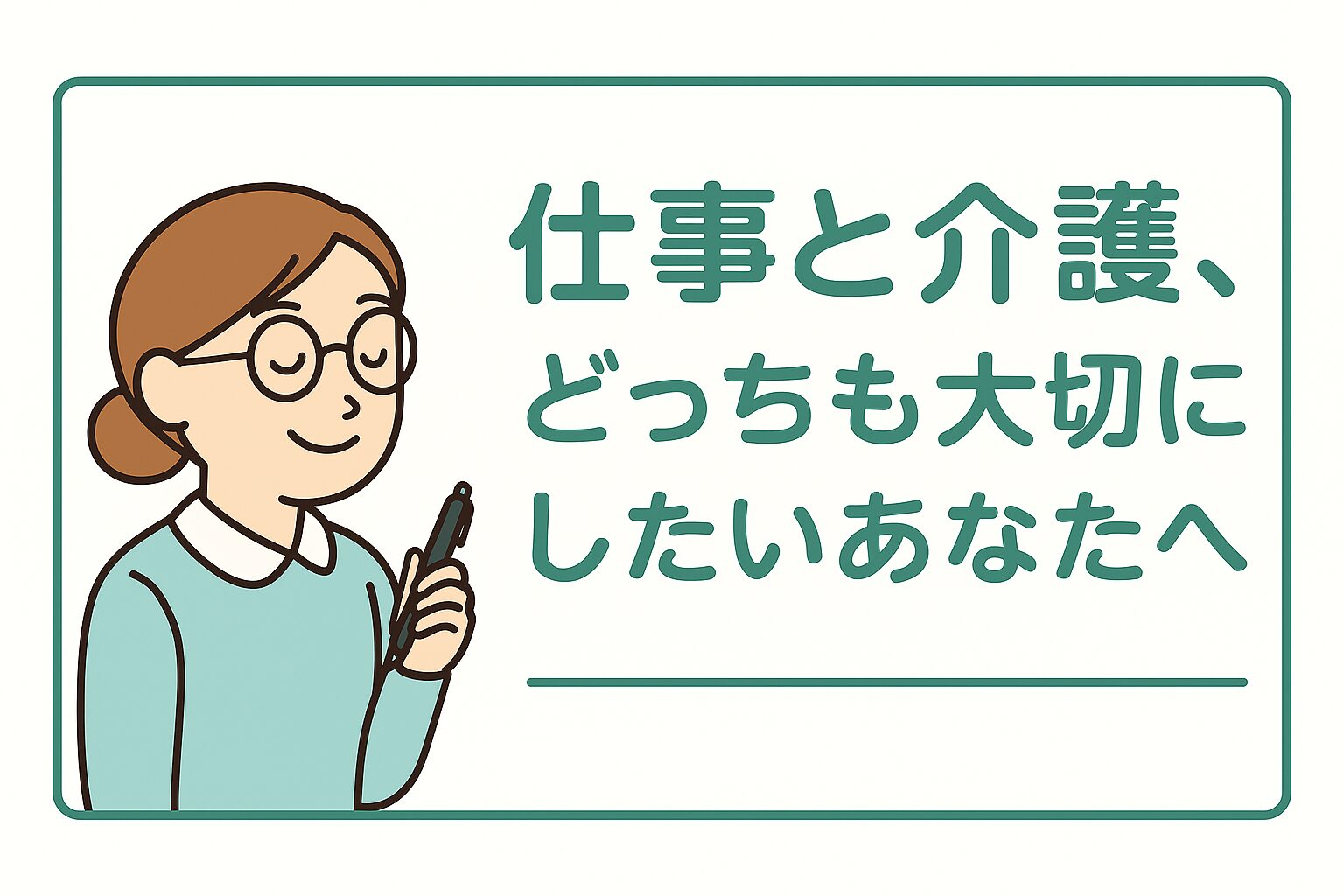


コメント