〜知っておきたい、介護保険申請と介護サービス利用までの流れ〜
はじめに

親が倒れて介護が必要になった・・・どこに相談したら良いんだろう?
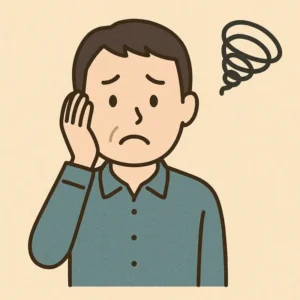
親が高齢になり、一人暮らしが心配・・・ヘルパーさんはすぐに来てもらえる?
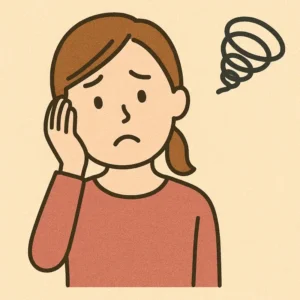
親の認知症がすすんできたみたい・・・デイサービスに行けるかな?
このようなとき、介護保険のサービスを利用することができます。
介護保険サービスを使えば、デイサービスやヘルパーなど、頼れる支援を受けられます。
でも、すぐに使えるわけではありません。
「介護のことってどこに相談するの?」「介護サービスと使うまでにどのくらい時間がかかるの?」
はじめての介護は、わからないことだらけです。
このページでは、介護保険の申請からサービス利用までの道のりを、くわしくご案内します。
介護保険を使うまでの流れ
まずは、介護保険サービスを利用するための大まかなステップを見てみましょう。
介護保険サービス利用の6ステップ
- 介護保険を申請する
- 認定調査を受ける
- 主治医が意見書を提出する
- 介護認定結果が届く
- ケアマネジャーと契約する
- ケアプランを作成して介護サービス開始
スムーズに進めば、申請から1か月〜1か月半ほどで介護サービスの利用が始まります。
介護認定が出る前でも、介護サービスを利用できる場合があります。
例えば、病院からの退院が決まり、早く介護サービスを利用したい場合は、介護認定結果が出る前でも仮の介護度を想定して介護サービスを利用することができます。
Step① 要介護認定を申請する
介護保険サービスを使うためには、まず「介護認定」の申請をして、介護認定を受ける必要があります。介護認定は本人の状態を表す区分で、区分ごとに利用できるサービスの量が決まります。

介護の認定は軽度の要支援1・2と、要介護1〜5まであります。
要介護5は受けられる介護サービの量が一番多い区分です。
どこに申請するの?
- お住まいの市区町村の介護保険の担当窓口
介護保険課・高齢福祉課 等名称はさまざまです。
わからない場合はお住まいの各役所で問い合わせましょう。 - 地域包括支援センター
日常生活圏域(概ね中学校区)に1箇所設置されています。
誰が申請するの?
- 本人または家族や親族(代理申請OK)
- ケアマネージャーや病院のソーシャルワーカー等でも代行可能
申請に必要なもの
- 介護保険被保険者証(65歳以上の人に配布されている証書)
- 健康保険証(40~64歳の場合)

保険証を紛失して手元にない場合でも申請できるので、窓口に相談しましょう。
代理で申請する時は、その方の身分証明が必要になることがあります。
Step② 認定調査を受ける
申請後、市町村の職員または委託調査員が本人の心身の状態を確認するために訪問調査(面談)を行います。
調査のポイント
- 自宅や入院先や施設で30〜60分ほどの聞き取り
- 足や手の動き、起き上がりや歩行等の動作、食事やトイレの様子、記憶力などの確認
- 家族など本人を知る人が立ち会って、普段の様子を補足できると◎
認定調査の時に、高齢者の方は普段やれないことを「できる」と言われたり、いつもならできない動作でもがんばってやってしまうことがあります。
例えば、
・いつもは立ち上がりに手助けが必要だが、調査の時にがんばってやれてしまった
・いつもは言えない自分の生年月日が言えた
できないことがやれること自体はとても良いことですが、それでは普段の様子が調査員に伝わりません。
認定調査の時は、〝テストを受ける〟というような緊張感が芽生えやすくなります。
そうすると普段の本人の状態とは異なる結果になりかねません。
本来の介護度より軽く出てしまった、ということはよくあります。
そのために認定調査の時は、普段の様子をよく知る家族や友人、病院の職員等が立ち会い、いつもの様子を補足説明できると良いでしょう。
Step③ 主治医の意見書が必要
市町村が主治医に「主治医意見書」の作成を依頼します。
この意見書と認定調査の結果をもとに、介護の区分が判定されます。

主治医の意見書は、役所から直接医師に依頼するので、本人や家族が医師にお願いする必要はありません。
ただ、直近で診察を受ける時に主治医へ、介護保険を申請すること、普段の様子等を伝えておきましょう。
するとその内容が意見書に反映されるので、状態に見合った介護度が出やすくなります。
Step④ 認定結果が届く
基本的に申請から約30日以内に、認定の結果通知と、「介護保険被保険者証」が郵送されます。
介護申請の混み具合や主治医意見書の遅れ等で結果が出るまでに30日以上かかることもあります。
介護度の区分
- 【非該当】:介護保険サービスは使えない
- 【要支援1・2】:軽い支援が必要
- 【要介護1〜5】:日常生活に支援が必要
認定区分によって、使えるサービスやサービスの量が異なります。
Step⑤ ケアマネジャーと契約する
要介護1〜5に認定された方は、居宅介護支援事業所のケアマネジャーと契約して、利用する介護サービス決めます。
ケアマネジャーとは?
- 利用者や家族から希望や困りごと等の話を聞き、状況を把握してそれを改善するための計画を立てる
どうやって探す?
- 地域包括支援センター、役所・病院の窓口などで紹介してもらう
- インターネットで調べたり、知人から聞いたりするなどして自分で調べる

ケアマネージャーが所属する事業所には特徴があります。
例えば、病院やクリニックに併設している事業所は、医療連携をはかりやすいです。
特別養護老人ホームやデイサービスなどに併設されている事業所は、それらのサービスの相談がしやすくなります。
Step⑥ ケアプラン作成 → サービス利用開始!
ケアマネージャーと面談して、本人の希望や状態に合わせたサービスの組み合わせ(ケアプラン)を作成します。
たとえば:
- 通所介護(デイサービス)
- 訪問介護(ヘルパー)
- 訪問看護
- 訪問リハビリ
- ショートステイ(短期間の宿泊サービス)
- 福祉用具のレンタル など
サービス開始までの目安
- ケアプランを作成し、利用する介護サービスと契約した後から介護サービスを利用できます。
- 状況によっては即日調整しサービスが開始されるケースもあります。
申請からサービス利用までのモデルケース(目安)
| 日数 | 内容 |
|---|---|
| 1日目 | 要介護認定を申請 |
| 7日目 | 認定調査を受ける |
| 10日目 | 主治医意見書が手配される |
| 30日目 | 認定結果が届く |
| 35日目 | ケアマネと契約・サービス調整 |
| 40日目〜 | 介護サービス利用スタート! |

各ステップがスムーズに進めば、1か月〜1.5か月ほどで利用可能です。
利用者や介護者の状況により、介護認定結果が出る前でも利用できることがあります。
よくある質問(Q&A)
Q. 認定の結果が出るまでに困ったらどうするの?
→介護申請後、認定調査や主治医意見書をもとに、まずはコンピューターによる判定が行われます。(一次判定)
その結果をもとに、介護度を予測して介護サービスを利用することができます。
その場合、見込んでいた介護度と、実際の介護度に相違がある場合は、超過した部分が自費(介護保険対象外)となり、利用料金が高額になる場合があります。
介護認定が出る前に介護サービスを利用する場合は、利用料金がどのくらいになるか担当のケアマネージャーに確認しておきましょう。
Q. ケアマネは選べるの?
→ はい、選べます。合わない場合は変更も可能です。人間同士のやりとりになるので、相性が合わないと感じたら、交代してもらうことも考えてみましょう。
Q. 「非該当」だったらどうすれば?
→ 軽度なサポートが必要な場合、地域の介護予防事業や民間の支援サービスを利用できることがあります。
おわりに|焦らず、ひとつずつで大丈夫
はじめての介護は誰でも不安です。
でも、大丈夫。
今できることをひとつずつ進めていけば、ちゃんと道はひらけていきます。
不安なときは、地域包括支援センターやケアマネージャーに相談しましょう。
そしてこのブログも、あなたの「心の相談窓口」になれたら嬉しいです。
介護のことをお話する「まげ」でした🍵
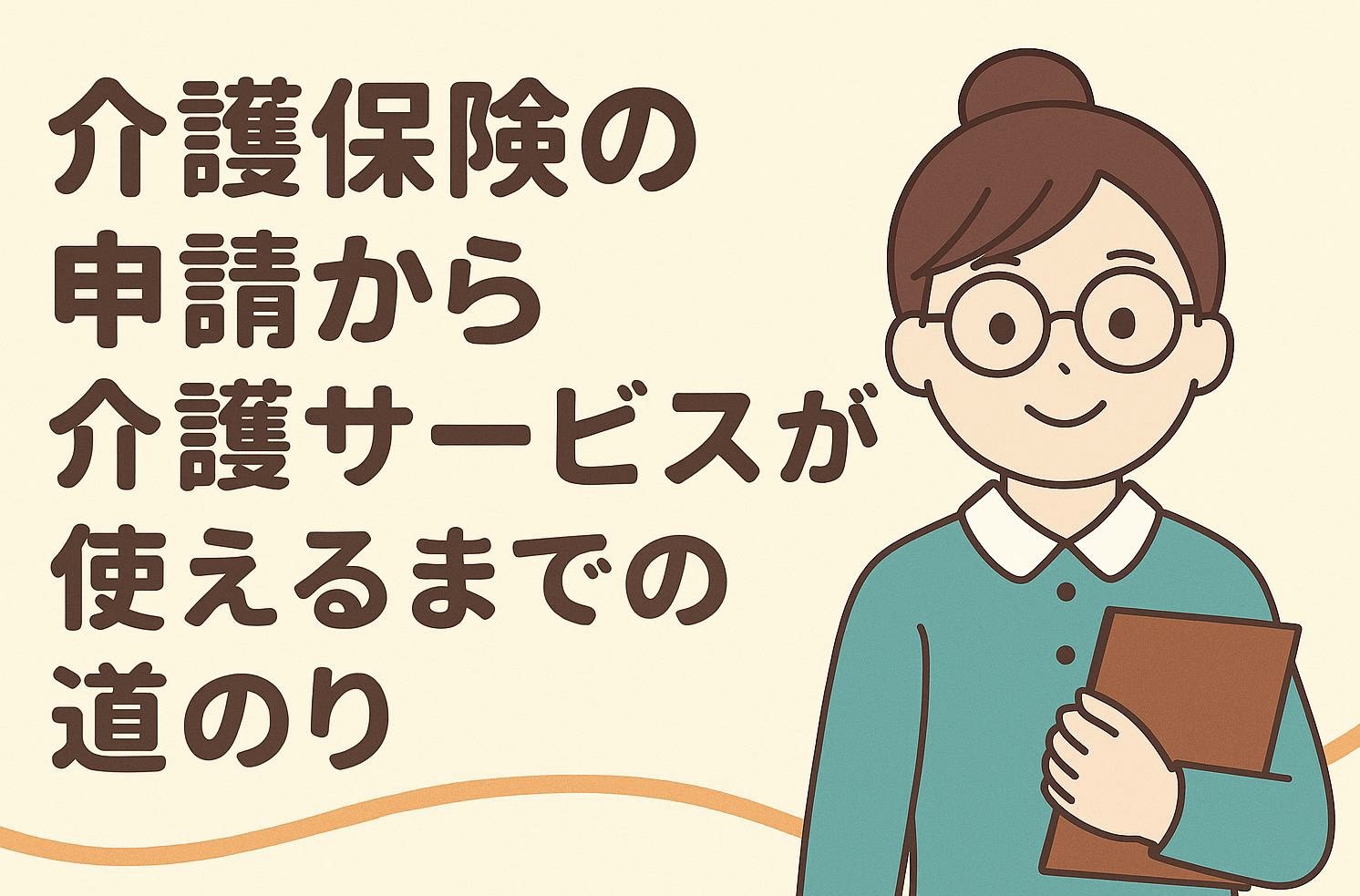


コメント