父の暮らしから見える変化
Aさんは87歳の男性。20年前に妻を亡くしてから一人暮らしを続けています。
子どもは長女と長男の2人。関係は良好で、それぞれ家庭を持ち、長女は隣県、長男は遠方の他県に住んでいます。
長女は月に一度ほどAさんを訪ね、一緒に買い物や食事を楽しんでいました。
ある日、長女はAさんの運転する車に同乗し、いつものスーパーへ買い物に向かいました。
店までは車で10分ほど。通い慣れた道のはずでした。
しかし出発して間もなく、Aさんの様子がおかしいことに長女は気づきます。
どうやら、スーパーへの道が分からなくなってしまったようでした。
表情は険しくなり、焦ったAさんは赤信号の交差点へ進入してしまいます。
幸い事故にはならずに済みましたが、長女は胸が凍る思いでした。
店に到着すると、Aさんは普段通りの様子に戻り、いつものように買い物を済ませました。
帰り道の運転も落ち着いたもので、特に問題はありませんでした。
しかし帰宅後、長女が恐る恐る先ほどのことを尋ねると、Aさんは何も覚えていませんでした。
あの険しい表情を思い出しながら、これ以上問い詰めるのはやめようと長女は思いました。
けれど、その胸には拭いきれない大きな不安が残りました。
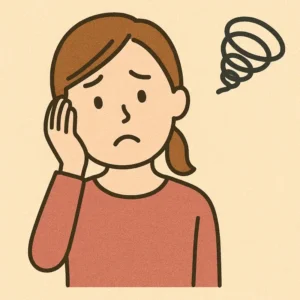
お父さんどうしちゃたのかな。
最近ちょっと様子がおかしいし・・・
このまま車の運転をさせていていいのかな・・・
長女は、この日の出来事を長男に伝えました。
すると長男も、以前から父・Aさんの様子に「おかしいな」と感じることがあったと話しました。
翌週、長男は帰省し、Aさんの車にドライブレコーダーを取り付けました。
遠隔で映像を確認できるようにし、Aさんの運転を見守ることにしたのです。
やがて記録を確認すると、普段は行かない場所へ向かう運転の記録がいくつも残っていました。
中には、警察官と道端で話をしている場面まで映っていました。
その映像を見た長男は、胸の奥がざわつくような不安を覚えました。
一方で、長女は訪問するたびに車の外装を点検し、傷やへこみがないか確認していました。
「父に何かあったのではないか」――そんな心配がいつも頭をよぎっていたのです。
しかし、そうした子どもたちの心配をよそに、Aさんは笑顔でこう言いました。
「おれは車の運転はうまいんだ。心配しすぎだよ、大丈夫だ。」
その言葉の裏にある「自分を失いたくない気持ち」のようなものを、長女も長男も感じ取っていました。
けれど同時に、現実の危うさが二人の心に重くのしかかっていきました。
一人暮らしと小さな変化
それから、Aさんの暮らしには少しずつ変化が表れました。
長女が気づいたのは――
- 同じものを何個も買ってくる
- 冷蔵庫に食品を腐らせたままにしている
- 電話の会話がちぐはぐになっている
- 詳しく聞こうとすると、急に怒り出す
それまでの穏やかなAさんからは想像できない姿に、長女は大きな不安を抱きました。
ある日、Aさんの車のドアに大きなへこみがあるのを見つけました。
「どうしたの?」と聞いても、Aさんは答えません。
さらにたずねると、「ちょっとこすっただけだ!」と声を荒らげました。
普段は温和な父が怒鳴ったことにも、長女はショックを受けました。
心配になった長女は、市の高齢福祉課に介護保険を申請。
やがてAさんには 要介護1の認定 が下りました。
そして家族の説得と車の売却により、Aさんは車の運転をやめることになりました。
移動手段を失ったAさんの暮らしは、少しずつ介護サービスに支えられるようになっていきます。
買い物はヘルパーに依頼。週に2回、掃除や洗濯、そして見守りもお願いしました。
また、時々長女がネットスーパーを利用して好物を届けると、Aさんはとても嬉しそうに受け取りました。
その笑顔は昔からの父の姿のAさんで、長女はほっとしたのでした。
Aさんは確かにそこにいます。
デイサービスと友人の支え
外出の機会がめっきり減ってしまったため、Aさんは週2回のデイサービスを利用することになりました。
入浴や運動、そして人との交流の時間ができ、家に閉じこもりがちだった暮らしに少し活気が戻ってきました。
また、長年の親しい友人が時々Aさんの家を訪ね、一緒に食事をすることもありました。
長女はその友人とも連絡を取り合い、Aさんの近況を共有しました。
そうすることで、友人からも「今日はこんな様子でしたよ」と知らせてもらえるようになり、地域のつながりが心強い支えになっていきました。
認知症の進行とトラブル
さらに認知症が進み、Aさんの暮らしには新たな困りごとが増えてきました。
物をなくす、おふろに入らない、家事ができなくなる……。
それまでできていた日常のことが少しずつできなくなっていったのです。
そんな中、Aさんの友人から長女に一本の電話が入りました。
「Aさんの家に、見慣れない女が出入りしているようだ。」
心配になって調べてみると、Aさんが毎月受け取っていた生活費を、その女が言いがかりをつけて奪っていたことが分かりました。
信じがたい出来事に、家族は言葉を失いました。
長女はすでに成年後見人となって金銭管理を行っていましたが、この件をきっかけに現金の送付を完全にやめました。
さらに、自宅には見守りカメラを設置。防犯対策だけでなく、日々の暮らしの確認もできるようにしました。
カメラには音声通話の機能があり、長女はそこから声をかけることができました。
「お父さん、薬は飲みましたか?」
呼びかけに応じてAさんが薬を口にする姿が映ると、遠くにいても支えられている実感がありました。
徘徊と家族の決断
ある寒い冬の日のことでした。
見守りカメラには、ジャンパーを羽織ったAさんが家を出ていく姿が映っていました。
しかしその後の行方が分からず、長女は慌てて警察に相談しました。
約8時間後、隣市の繁華街でAさんは保護されました。
軽い脱水症状とふらつきがありましたが、大事には至りませんでした。
けれど、家族にとっては「もし誰にも見つけてもらえなかったら…」という恐怖が残りました。
その後、トイレの失敗も増え、在宅での暮らしは限界に近づいていきました。
長女と長男はケアマネジャーに相談し、介護施設への入居を決断しました。
候補となる施設をいくつか見学・調査した上で、認知症専門のグループホームを選びました。
すぐには空きがなかったため、ショートステイを利用しながら入居を待ちました。
そして入居が決まった時、Aさんの介護度は要介護3に上がっていました。
まとめ:遠距離介護のむずかしさと支え合い
遠距離介護では、日々の小さな変化に気づきにくく、その分家族の不安も大きくなりがちです。
けれど、ヘルパー、デイサービス、地域の友人、そして見守りカメラといった支援の積み重ねが、Aさんの暮らしを支え続けました。
最終的にはグループホームという選択になりました。
それは決して後ろ向きなものではなく、「本人が安心して暮らせる場所」を見つけられた証でもあります。
家族へのメッセージ
離れて暮らす家族にとって、介護には「ちゃんと見てあげられない」という罪悪感がつきまといやすいものです。
けれど大切なのは、
Aさんの暮らしを守ること
すべてを自分たちだけで背負わないこと です。
地域のサービスや専門職、そして周囲の人とのつながりを頼ることで、遠距離でも安心はつくれます。
「支え合える人がいる」ということ自体が、介護を必要とする人にとってもご家族にとっても大きな力になるのです。
遠距離介護のポイント
- 遠距離介護では、小さな変化に気づく仕組み(見守り・連絡・地域の協力)が大切
- 金銭管理や安全の工夫(成年後見人・見守りカメラなど)が安心につながる
- 最後まで自宅が難しくても、安心して暮らせる場所を見つけることがゴール
※本記事は実際の支援をもとに、個人が特定されないように十分配慮し、内容を一部変更・再構成しています。



コメント